Apple製品がアカデミック価格で購入できる。
そんな「学割」の魅力につられて放送大学(情報コース)に2021年9月より入学しました。
2022年1学期(2022年4月〜2022年9月)は僕にとって、2期目の学期となります。
1期目については、次のページに書きました。
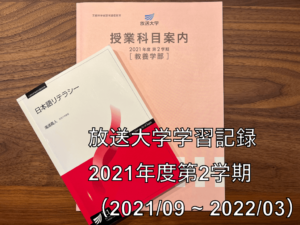
入学目的は学割という邪な目的ではありました。
しかし、いくつか科目を受講すると、「とても勉強になる!」と実感しました。
無理のない範囲で単位を取得し、最長在籍期間の10年間で卒業を目指してます。
2022年1学期が終了しましたので、単位取得状況、学割利用状況について書いて行きます。
2022年1学期概要
受講科目
| 科目 | 単位数 | 授業形態 | 成績評価 |
| データベース | 2単位 | 放送授業 | A |
| 日本語リテラシー演習 | 1単位 | オンライン | A |
| 問題解決の進め方 | 2単位 | 放送授業 | A |
今期の受講科目全てでAを取得することができました。
特に「日本語リテラシー演習」はレポート数がかなり多く大変な科目であったので、A評価で嬉しいです。
学習時間
日中は働いている社会人学生です。
そのため、学習時間は夜もしくは週末となります。
放送授業は、1講義45分です。
放送大学のシステムWAKABAを使って動画を再生し、受講しました。
再生速度を調整することが可能です。
放送授業は、1.5倍速で再生して受講しました。
1.5倍速再生でもちょっと早口に感じるかも?程度の話すスピードのため、支障なく受講できました
テキストありの場合は、放送授業の前に予習としてテキストを読みます。
1講義分あたり、30分程度あれば読み終えることができます。
そのため、1科目に必要な学習時間は、予習30分 + 放送授業 30分(45÷1.5) = 60分(1時間)となります。
つまり、1時間 / 1科目 / 週 程度の時間が必要となります。
今期の学習時間は、3時間/週程度でした。
しかし、日本語リテラシー演習はレポート課題が多く、レポートの進捗が悪いと学習時間が週〜5時間程度になることもありました。
僕の場合、今期程度の負荷量、1学期あたり3科目程度が自分にあっていると感じてます。
しかし、最長在学期間の10年で卒業を目指すとしても、3科目/1学期では単位がちょっと足りなくなるのでは?と危惧してます。
まだ1年目が修了したばかりのため、まずは慣れることを優先してゆっくり単位を積んでいくつもりです。
卒業が見えてきたら、取得単位について計画を立てる予定です。
費用
27,500円
内訳は次のようになります。
放送授業: 2科目(2 x 2 = 4単位) x 11,000円(テキスト代込み)= 22,000円
オンライン授業:1科目(1単位) x 5,500 = 5,500円
取得科目
日本語リテラシー演習
「日本語リテラシー」の学習内容について、実践形式で学習する科目です。
講義の目的は、「わかる文章」を書くことです。
「日本語リテラシー」が面白い講義だったので、その演習科目である本科目を受講しました。
とにかくレポートの数が多い科目でした。
講義数は、8回と放送授業の約半分です。
しかし、学習時間は「レポートを書く」が意外と時間を要するので、他の科目と同等程度だったと思います。
何気なく話して、書いている日本語に対して向き合う機会はなかったので、勉強になりました。
「文章の種類」、「接続詞」、「論理」などなどあまり意識してなかったことをについて認識する、学ぶことが出来る良い科目でした。
提出レポートについてもライティングチューターの方からの添削結果が返却されます。文章を他人に見てもらうことで気をつけるべきポイントを確認できて良かったです。
問題解決の進め方
仕事にも必ず役に立つだろうと思い取得した科目です。
この講義を受講したことで問題に対する捉え方が変わりました。
まず、「問題をどのように捉えるべきなのか。」について理解が深まりました。
その中で、問題、そして問題解決に関してキーワードとなる単語とその意味をここにも書いておきます。
問題 : 「あるべき姿」と「現状」とのギャップ。
課題 : その「ギャップ」を埋めるためにすべきこと。
目標 : あるべき姿への途中
目的: 成し遂げようとする事柄
「あるべき姿」をすぐに目指すことができなくても、現象より少しましはないかを考える。
次に、題解決にあたっての一般的な知識を知ることができて良かったです。
知ってるだけの差で「こういうもんだ」を自分を納得させ、諦めとも言えるかもしれませんが、より良い行動に繋がると思います。
特に印象的だったものは、「2・6・2の法則」です。
これは、組織で問題解決に取り組む場合にその構成員は、「2割:問題解決に意欲が高い人」、「6割:意欲が高くも低くもない平均的な人」、そして残りの「2割:意欲が低い人」に分かれるというものです。
この比率は、人員の増加や抜けなどにより、構成が変わっても維持されるというのです。
知らないと「自分はこんなに頑張っているのに他の人は。。。」ような思考に陥ってしまう危険があります。
知ってるだけで「こんなもんだから」っとある意味開き直ることが出来ると思います。
データベース
データベースを取り扱うための言語であるSQLを本で勉強しました。
しかし、データベースについては、漠然としたイメージしかありませんでした。
当科目取得により、基礎からデータベースについて学習できると思い取得しました。
データベースの基礎、関連用語を学ぶことが出来て勉強になりました。
データベース = データの集合体であるこのは、受講前から漠然と認識していました。
それ以上でもそれ以下でもなかったのですが、データベースを次のように捉えることが出来るようになりました。
適切な判断をくだしたり、意志決定したりするための役立つ資料や知識としての目的を持って客観的な事実としてのデータが集められ、コンピュータ上に格納されたものがデータベースである。
データベース 辻 晴彦、芝崎 順司著 (放送大学 テキスト)
データベースを作成するときは、目的について、よく考え、その目的を達成するためにはどのようなデータが必要かを意識することが大切だと実感しまいた。
適当に作成してしまい、結局いらなかったな、だったり、後から構成を大幅に変更してしまうことが多々あるので改善できるきっかけになりそうです。
まとめ
今回は、放送大学 2022年1学期学習記録について書きました。
当学期修了で放送大学に1年在籍したことになります。
今回は、情報系科目を1つ、その他科目を2つ受講しました。
特に情報系科目は、これまで本で学習してきた内容とは異なり、より基礎的なことを体系的に学べた点で放送大学講義のメリットがありました。
他2科目については、これまでなんとなく書いていた日本語、なんとなく問題にぶつかってなんとなく解決?してきたことに対して、行動が変わるきっかけになったと思います。
最後に読書での知識習得は、インプットのみになりがちで読んだだけになりがちです。
放送大学での単位取得は、単位試験、レポートなどのアウトプットが強制的に求められるため、ただ本を読むよりは、自分の糧になってそうです。(本を買う何倍も費用がかかっていることもありますが。。。)
最後まで読んでいただきありがとうございます。

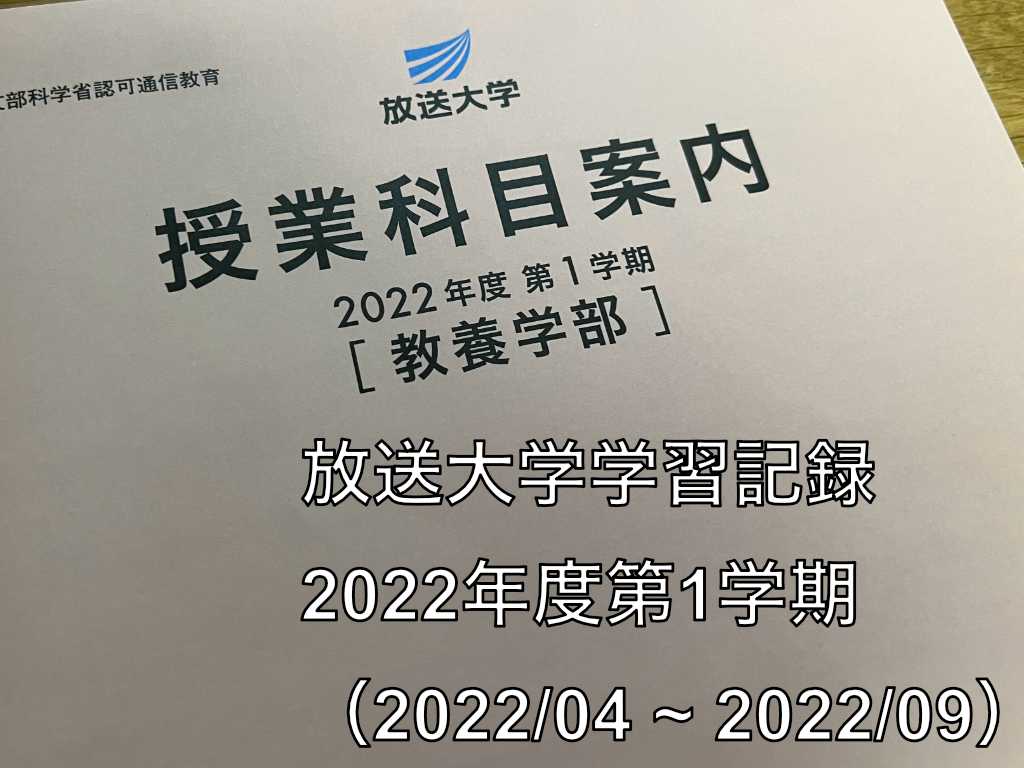

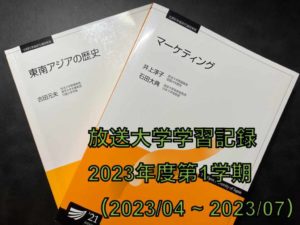
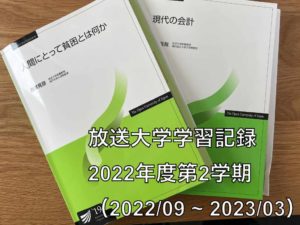
コメント